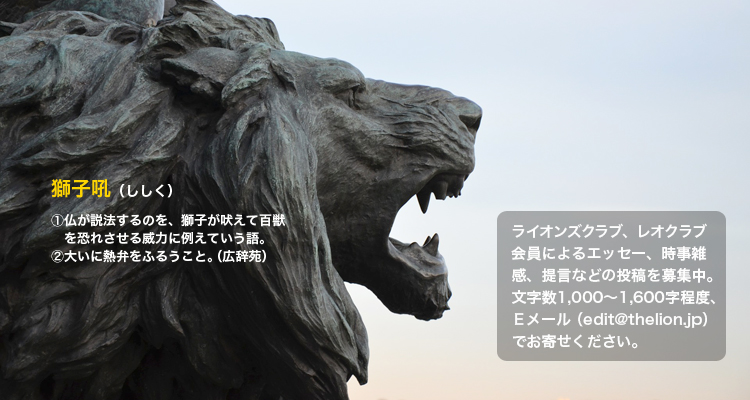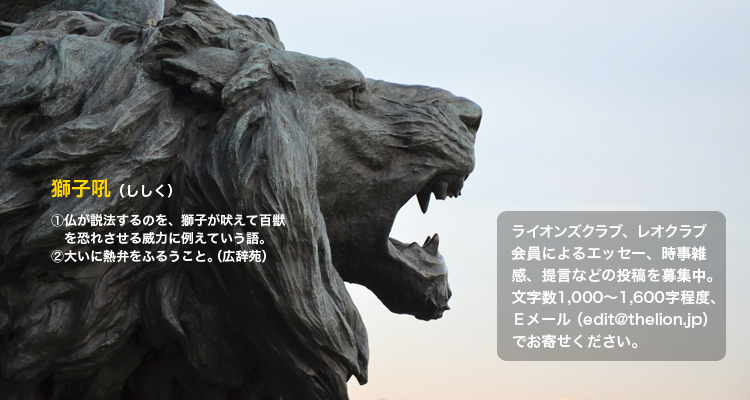獅子吼
本宿用水の
世界かんがい施設登録
髙田泰久(静岡県・長泉LC)
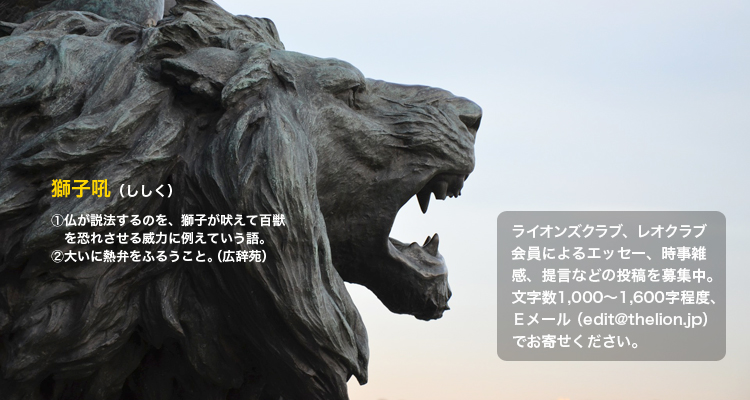
私の地元・静岡県東部に位置する長泉町本宿には「本宿用水」が流れ、そのせせらぎは農業用水のみならず多目的に活用されて地域を潤しています。私は地域の歴史的遺跡や文化に関心を持ち、幼い頃から本宿用水に親しみを持ってきたことから、先人が残してくれた遺産を保全し、その歴史を後世に残したいと活動しています。そこで、本宿用水の歴史と世界かんがい施設遺産登録への取り組みや関連する諸活動について紹介したいと思います。

鎌倉時代の長泉町本宿は、京から関東に向かう主要街道であった足柄街道の黄瀬川宿に属し、旅人を泊める旅籠(はたご)屋などが軒を連ねた活気ある村であったと伝えられています。その後、足柄街道は富士山の噴火や黄瀬川の氾濫(はんらん)などで道筋が変わると共に、主要街道は箱根越えの東海道に変わっていきました。そのため本宿村は寂れ、農業を中心とする村に変わりました。本宿村の近くには一級河川の黄瀬川が流れていますが、河床との段丘差が大きいため川の水を稲作に利用出来ず、アワやヒエなどの雑穀に頼る貧しい村でありました。
1601年、本宿村の名主髙田久左衛門は、徳川家康に命を受けた興国寺城主で領主となった天野三郎兵衛康景(以下、天野康景)に、黄瀬川鮎壺の滝上流から隧(ずい)道を掘って用水を作ることを嘆願しました。天野康景は、村人のみの人足で掘削し費用も村が負担することを条件に許可しました。髙田久左衛門は村人を集め、当時の最先端技術であった「甲州流水利法」による掘削を行い、1603年に500m余の隧道と約2㎞の水路から成る本宿用水を完成させました。天野康景からは「10石分の無年貢地を与えるから管理を徹底するように」と証文をもらっています。本宿村は本宿用水が出来たことで新田開発が進み、その後の検地の度に石高が上がっていることが古文書等から分かります。本宿用水設置から68年後の1670年に完成した「箱根用水」は箱根の外輪山を素掘りで堀り抜いて芦ノ湖から取水しており、本宿用水の掘削技術を手本としたと伝えられています。

世界かんがい施設遺産とは、インドのニューデリーに本部を置く国際かんがい排水委員会(ICID)が、建設から100年以上が経過した施設を登録表彰しているものです。灌漑(かんがい)の歴史・発展を明らかにし灌漑施設が適切に保全されることを目的として、現在19カ国に177件が登録されています。
私は、住民の悲願として造られた本宿用水の歴史的価値と、今日まで維持管理を続けてきた地域住民の思いを後世に残すために、世界かんがい施設遺産に登録したいと考えました。そこで、遺産候補としての申請を農林水産省に提出し、「国際かんがい排水委員会日本国内委員会」の審査に合格してから、国際申請のための英文申請書を作り、同省を通じて国際かんがい排水委員会へ提出しました。
2023年9月に登録可能の内示を受け、同年11月4日にインドの東海岸にある都市ヴィシャカパトナムで開催された国際かんがい排水委員会の理事会を経て登録が確定されたため、私は現地に臨み登録証の授与を受けました。申請には多くの方の支援を頂き、晴れて登録されたことは感慨深いものがあります。同年の日本の登録施設はこの本宿用水と、静岡県富士宮市「北山用水」、山形市「山形五堰」、岡山市「建部井堰」の4施設で、現在、国内では54施設が登録されています。
登録されて世界の宝となった本宿用水を後世に残すために、私はさまざまな活動を行っています。ライオンズクラブの例会や各種団体での説明会、地域住民による土砂上げ等の保全作業、田んぼで子どもたちを遊ばせる「本宿用水ドロリンピック」の開催、用水ルート見学会などです。また、国内の登録施設間で情報交換を行うと共に、ホームページやSNSを活用して多くの方に「本宿用水」知っていただけるように取り組みを続けています。
(2006年入会/78歳)
2025.02更新

 ライオン誌日本語版ウェブマガジン
ライオン誌日本語版ウェブマガジン