歴史
幼児難聴をより早く発見し
言葉のある世界へ
1970年代

赤ん坊は生まれた時からさまざまな音を耳にする。家族の声、医師の足音、そして自分の心音など。母親のおなかにいた時とは違う世界に足を踏み入れ、音や言葉のシャワーを浴びながら成長していく。しかし、難聴児の場合はそれがさえぎられており、聴力だけでなく精神や知能、社会性など全般的な発達に影響が出る恐れがある。難聴のより早い発見と適切な対処により、そうした影響は大幅な改善が見込めるにもかかわらず、1970年代の日本の難聴児対策は不十分で、欧米より30年は遅れていると言われていた。
この頃、難聴児問題に着目したライオンズによる奉仕活動が日本各地で行われた。例えば四国4県と鳥取・岡山で構成する地区のライオンズは、合同で難聴幼児通園施設「香川こだま学園」を設立した。高知市第六小学校の難聴学級は、高知市のライオンズクラブが開設したものだ。長野県のライオンズは幼児難聴の早期発見の重要性を分かりやすく説明したパンフレットを作成し妊産婦などに配布した。そして以下に紹介するのは、福島県のライオンズの粘り強い働き掛けで実現した未就学幼児のための難聴言語障害治療室設置と、ある難聴児の母親による手記出版のあらましである。

74年当時、福島市内の聴覚障害児のための施設は、小学校の難聴学級とろう児のためのろう学校幼稚部しかなかった。福島中央ライオンズクラブに所属していた小関芳晃医師と酒井清明医師は、難聴や言葉に障害のある幼児を対象とした機関が必要であることをクラブに提案。スローガン「難聴児に音と言葉を」を掲げた活動がスタートした。
まずは市内全ての幼稚園・保育園児を対象とした難聴児実態調査を実施し、その結果を基に「幼児難聴の教育制度の確立を要望する陳情書」を県に提出した。しかし回答は、「担当部課が無い」「文部省と厚生省にまたがる分野なので難しい」とにべもない。そこで福島中央ライオンズクラブを含め県北地域15クラブが合同で「幼児聴覚・言語障害センターを作る会」を発足。更に難聴児親の会、ことばの教育育成会とも手を携えて各方面に訴え続けた。活動開始から4年、12回目の陳情で、とうとう県は「3歳児から県立聾学校幼稚部に通学出来るよう学校規則等を改正すること、普通校での難聴学級、言語障害学級の増設、そして飯坂温泉病院内に幼児の難聴・言語障害治療訓練施設を置くこと」を約束した。これは日本初の公立の難聴幼児のための施設であった。病院で働く訓練士は、期待を込めて次のように話した。
「ここでは年間300人くらいの幼児が検診を受けます。これまでは正確な聴覚検査がなされずにきましたが、これからは難聴児の発見が増えるでしょう。施設が出来れば発見後の対策もしっかり立てられます」
78年10月、作る会は目的を果たし解散した。しかし難聴児対策の波はその後も広がり、公立幼稚園内での言語や聴覚に障害のある子のための指導室設置へとつながっていった(『ライオン誌』79年3月号)。

福島中央ライオンズクラブが難聴児問題に取り組み始める少し前、福島県郡山市で一人の男の子が誕生した。その子、佐藤昌也君は生後1カ月半の頃、鼻血と血便を出した。医者には風邪と言われたが、程なく今度は両耳から出血。溶血性貧血の疑いがあるとされ、月1回の治療を受けるようになった。1歳半で保育所に入所すると、他の子たちはカタコトの言葉が日々変化していく中で、昌也君だけは言葉を発しなかった。
母親の法子さんは言葉の遅れを心配し、昌也君が2歳8カ月の時に東京にある国立病院を受診した。すると「重い難聴の疑いがあり、東北では正確な測定が出来ない。治療をするならこっち(東京)に転居するしかない」と告げられる。大きなショックを受け途方に暮れる中、偶然手に取った幼児雑誌に国立聴力言語障害センターの紹介記事を見つけ、わらをもつかむ気持ちで電話を掛けた。同センターは次年度まで予約が埋まっていたが、別の医師を紹介してもらうことが出来た。
紹介された帝京大学耳鼻科の田中美郷教授も、やはり昌也君を高度の難聴と診断した。しかし「努力次第できっと話せるようになる」とも言ってくれた。この言葉に支えられ、法子さんと昌也君の挑戦が始まった。週1回東京に通い帝京大学の言語治療教室で訓練を受け、自宅でも練習を続けた。健聴児の何百倍もの時間を掛けて一つひとつ言葉を身に着けていった。法子さんはそうした日々を詳細に記録した。
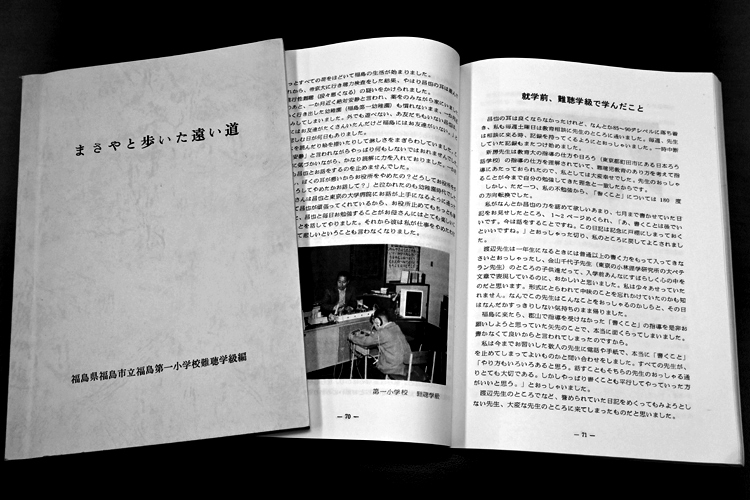
父の仕事の関係で福島市へ転居し、昌也君は福島第一小学校へ入学。難聴学級で新房佳夫教諭の指導を受けぐんぐん成長していく。そして新房教諭は、法子さんの手記と出会った。それは母としての不安や喜びを率直に記した、難聴児と母の克明な成長記録であった。
「悩みながら難聴児を育てている保護者の方々に読ませてあげたい」
そう考えた新房教諭は、日ごろから難聴児について話し合っていた福島中央ライオンズクラブの小関医師を訪ねた。
福島中央ライオンズクラブは手記の出版を快諾した。難聴児のための施設設置を実現させたばかりのメンバーたちにとって、次に取り組むべきは「心」の問題だった。80年3月、200ページに及ぶ『まさやと歩いた長い道』を1000冊刊行。朝日新聞や読売新聞、また全国の難聴児を持つ親の会の機関紙などで紹介されると、大きな反響を呼んだ。7月に350冊、8月には更に500冊を追加したが、たちまち在庫切れとなった。市内九つのクラブの協力も得て再販が繰り返された。手記を読んだ母親たちからは、「いかに学ぶべきか、ひしひしと伝わった」「子どものために何をしたら良いかはっきりと自覚した」など、感謝の手紙が殺到した。
86年、福島市立渡利中学校の生徒会選挙で、演台に立つ昌也君がいた。クラスで候補者として推されたのだ。
「この学校で補聴器をつけているのは僕一人なので、案外顔を知っている人は多いと思います」
と明るく力強く立候補演説を行い、4人の候補者の中から見事、副会長に当選した(『ライオン誌』87年6月号)。
2021.02更新(文/柳瀬祐子)

 ライオン誌日本語版ウェブマガジン
ライオン誌日本語版ウェブマガジン








